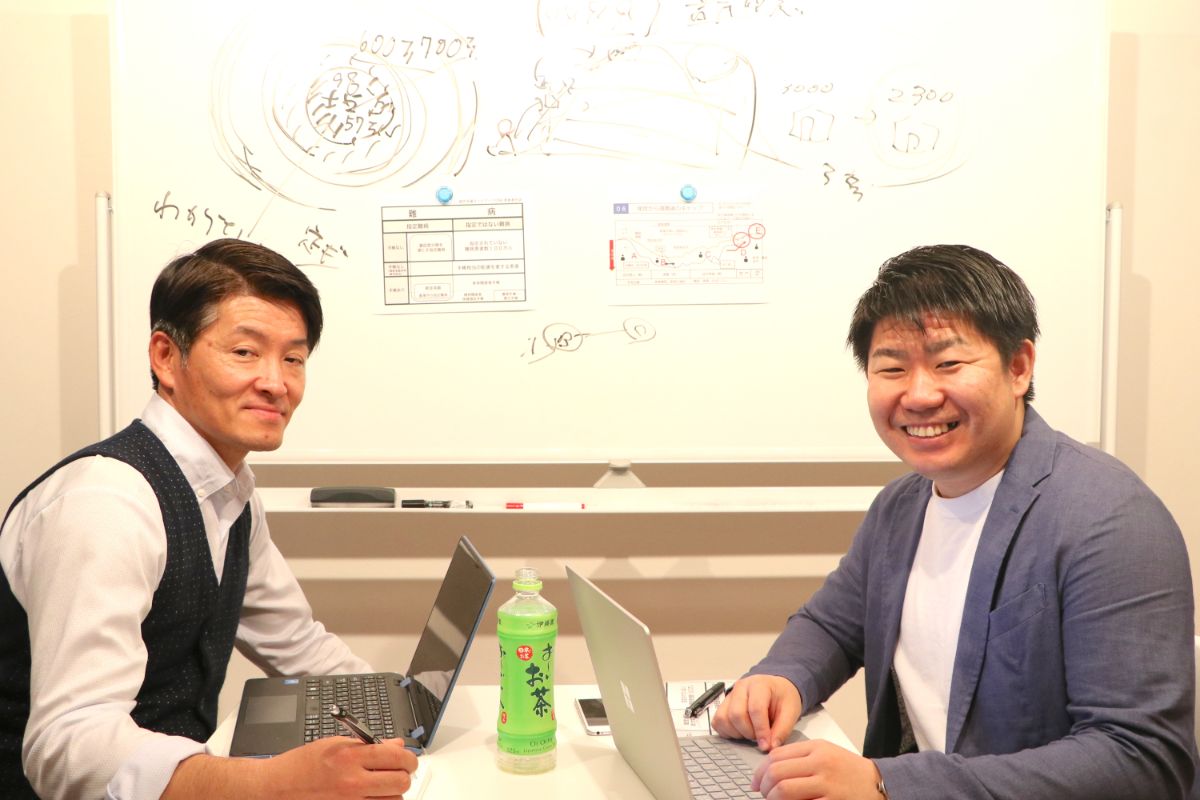
元難病患者就職サポーターと難病当事者でクロストーク
治療と仕事の両立って可能?
難病の患者さんのイメージについて
一般社会人では「職業によっては就職が難しい」(31.8%)の回答が最も多く、人事・総務関係者では「職場の理解・配慮があれば、治療と仕事の両立が可能」(34.8%)の回答が最多となりました。
「難病・IBDの就労環境に関する実態調査」より





ただ、障害者手帳を持っていない場合、どこまでの配慮が必要か会社としても悩ましい面がありそうですね。
私の場合、無理な残業さえしなければ問題なく働けていました。
それでも職場の人間関係レベルの配慮だけだと、やはり忙しい時に配慮しきれないタイミングが来ます。
そのタイミングが命取りになって当事者は潰れてしまうことが高いように思います。


患者さんと医療従事者が一緒に治療目的や方法を決めていくことを主眼にしたもので、このサービス自体はクローン病と潰瘍性大腸炎が対象のようです。
自分の病状、痛み・ストレスのレベル、相談したいことなどを入力して、診察時に医師と共有するために活用されているそうです。
就活時などによく、自分の説明書を作られる人もいますが、こういったツールの就労版があるといいなと思います。



出来ないことばかり書いてしまって、「これを会社に出してどうなるの」って。笑
なので、先ほどのような記入するだけで自分の説明書が出来るならありがたいなと思います。


ただ、「通院が必要」「夜間睡眠が必要」くらいしか書かれていなかったので、これだけの情報では配慮事項までは伝わりにくいと思います。




ただ、その部長の口から周りに伝わることはなかったです。
なので、関わる人にはしっかりと自分の口で説明する必要がありました。




新たにお仕事をしたいと考えている方、お仕事を続けられるかどうかお悩みの方などからの相談を受けています。


難病患者就職サポーターがキーパーソンではあるけれど、人員リソースの問題と提供サービスに個人差があるのは問題かなと思います。


それに、私のような指定ではない難治性疾患の場合、どちらにせよ対応してくれないのかなと…。


ただその一方で、ハローワーク職員でも難病患者サポーターの事を知らない人もいたり…。






雇用促進法では3障害のみで、法律間のズレが生じています。
海外で難病の診断名がでると対象になる国もありますが、日本は対象になりません。
生活の支障の程度が障害者手帳相当の患者は、難病患者も法定雇用率の制度に含める必要があると考えます。


特に、指定ではない難病の方が制度に結びつかない為、認識もされにくく、置いてけぼりになっている状況に危機感を感じています。

難病の方と一緒に働くことについて
難病の方と一緒に働くことについて
難病の方と一緒に働くことについて、「心配・ためらいはない」(計37.1%)と回答した人の割合が「心配・ためらいがある」(計24.4%)
「難病・IBDの就労環境に関する実態調査」より
実際には、軽い方々から重い方々までおり、実態を知ることによって自分の認識がアップデートしていくんですよね。
見て、知って、わかることもあるんだなと。
強い疲労感や痛み・痺れ・疾患によっては強い眠気など、見た目だけではわからない症状もあることも、ぜひ知ってほしいです。


それ以外にも、「睡眠時間が7時間に満たない時は、薬が効かなくなるので眠くなる」「急に来るので、もし寝てたら起こしてほしい」とも伝えています。


理解してもらえるように伝えないと意味がないと思って過眠症の本を読んでいたら、先ほどの言葉を見つけたので使っています。




寝ることに対して理解があったので助かりました。


「すみません、症状です」と言い訳みたいになってしまうこともありましたが、伝え続けることは大事と思います。


就労支援の現場で実践してきた3つの視点

中金さん、これまでの就労支援の現場から、何か解決につながるヒントありませんか?!
実際に、ハローワークにいたときに使っていたものを3つほどシェアしますね。




それで仕事を探す期間が延び、その期間がまたブランクになっていくと、結果的にキャリアアップも叶わなくなってしまう…
そうならないようにと思って、就職マウンテンの図をつくりました。
山登りの入り口にいる方が、いきなり頂上を目指すと高山病になってしまうかもしれない。
登山に「高度順応」という言葉もありますが、いきなり正社員ではなく、職業リハビリやスキルアップ、福祉的就労も視野に入れることもときに必要。
そういった考え方が、就職や社会復帰の場面でも役立つではないかと思っています。




ただ、中には会社に渡す方もいて、そこに記載されている情報を踏まえて、結果的に会社側でも理解が進んだという方もいらっしゃいました。


さいごに

例えば、テレワークのように通勤なしでも働くことがメジャーになったり。
症状に合った働き方の仕組みがあれば、働きやすくなりますし、会社が期待する働きにもつながると思います。



実際に、家にいながらパソコンを使ったり、電話でやりとりしながらやってみたこともあります。
それなりのお金しかもらえないですけどね。笑


そういう意味で、就職という道以外にも可能性はありそうな気がしてきました。
知り合いにも、リヤカーで花を売っていたフラワーアーティストさんがいて、最終的には本を出すくらい有名になったり。
そういう型にはまらない生き方を選んでいる人達が周りにもけっこういました。


年齢的には就職が難しいと訓練校で言われたそうでした。
それでも、その方は59歳で社労士の資格を取って、本人の希望で病気を企業に応募時に開示され、そのまま社労士事務所に就職されていかれました。



定年退職や、老齢年金受給までが長くなり、通院しながら働く方々も増える。
人生のトランジション(移行、あるいは転機)が今、多くの方に訪れる可能性があります。
治療をしながら働く人が、どうしたら働きやすくなるのか?
今起こっていることに意識的でありたいと思います。

>>【無料】中金竜次さんに質問できるオンライン難病就職サポートコミュニティはこちら

- 本コンテンツは、特定の治療法や投稿者の見解を推奨したり、完全性、正確性、有効性、合目的性等について保証するものではなく、その内容から発生するあらゆる問題についても責任を負うものではありません。
- 本記事は2020年2月4日に公開されました。現在の状況とは異なる可能性があることをご了承ください。




