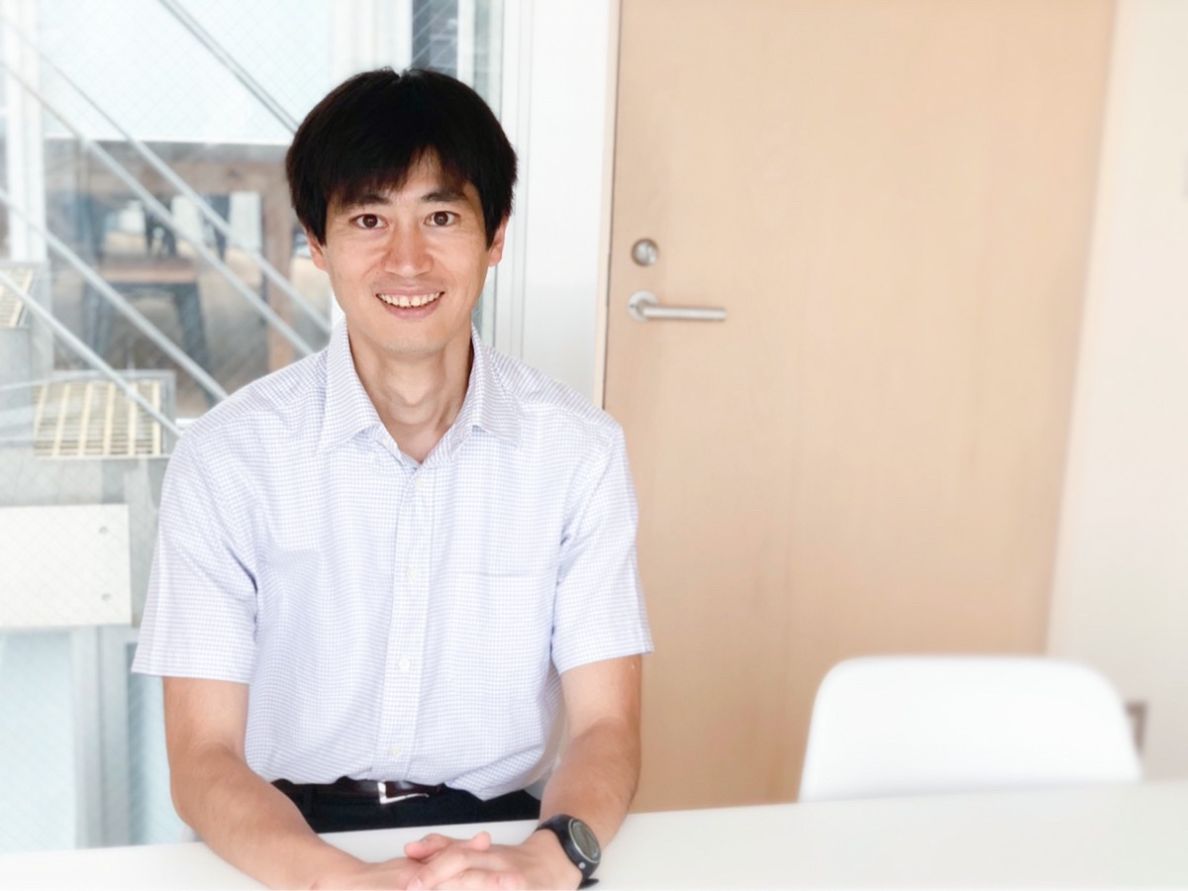
「スポーツを一生懸命できる才能があることは忘れないで」スポーツ精神科医の想い
選手にとって”なにがベスト”なのか探っていく

通常の精神外来と分けているのは、スポーツ精神外来の患者さんは別枠で、診療時間を確保しておきたいからなんです。


ただ、スポーツ精神外来を受診する方は、病名が付かない方が多いんです。そうすると、病気やお薬の説明よりも、その方がなにが原因でスポーツに関して悩んでいて、周りの環境はどうなっていて…など、診療を進める流れが通常とは異なるんですよね。
なので、スポーツ精神外来の独自の診療時間として、しっかり残しておきたいんです。


でも、スポーツ精神外来の場合は、安易に「つらいなら休んでください」とは言えないんです。スポーツの世界で休むことは、練習をしないことに繋がるので…。
選手にとって、なにがベストの対処法なのか、探っていく必要があるんです。




そもそも、練習を休もうと思えるかどうかも、なかなか難しいと思います。


活躍している選手は、その地位を守るプレッシャーから休めないこともあるでしょうね。逆に、レギュラーになっていない選手は、「今休んだらまた差を付けられる」と自分を追い込んでしまうこともあると思います。


ただ、精神的なことに詳しくないと、相談されてもどう対処していいかわからない人もいるんですよね。家族もそうで、厳しいことを言われてしまったこともありました。




「家族も、なんて言っていいかわからなかったんだと思いますが…」


家族にも、病院の先生にもそう言われてしまうと、もう他の人に相談しようとは思えなかったですね。

押さえつけてばかりでは、いつか潰れてしまう



悪口ではなくても、「このまえ上位に入っていたやつだ」と意識される世界ですからね。


コーチにも、相談しようとは思わなかったですね。すごく厳しい人だったので、「言ったらいけない」と思い込んでいたんです。
両親に言って、病院の先生に言って、それでも受け入れてもらえなかったことで、自分の心をシャットアウトしてしまったんです。




今は、コーチや監督を担う方が、メンタルの勉強をすることも増えたので、とてもいいことだと思います。ただ、昔はあまりそういった勉強をしている方もいなかったので…。いわゆる、昔ながらの“体育会系”のイメージに近い環境もあったのではないかと思います。
今も、その環境がなくなったとは言えないかなと。怒鳴って・叩いての世界ですよね。押さえつけるように指導して、伸びることを期待する。


ただ、ストレスをかけた後に、回復する時間が必要なんです。例えば、「雑草は踏まれて強くなる」と言いますよね。でも、ずっと踏まれ続けていたら、伸びる時間なんてないじゃないですか。
人間も同じで、ストレスを受けた分、心身の回復をさせてあげないと。押さえつけてばかりでは、いつか潰れてしまうだけです。


「休め」だけではなく、どうして休みが必要なのか、理由を説明してあげると安心するかと思いますよ。


選手のモチベーションを下げてしまう声かけとしては、選手がいい結果を出したときでも、「こんなもんで調子に乗るなよ」と言ってしまったりとか。


ただ、選手本人としては、自己ベストを出したことを否定されるのは、苦しいですよね。結果はちゃんと評価して、そこからもっと上を目指す方向に促してあげてほしいと思います。


ただ、指導する方に否定され続けている中で、自分を認めるのはとてもパワーがいることだと思います。その手助けとして、メンタルに携わる人間をうまく使ってほしいですね。手助けする立場の人間がいると、気がついてほしい。





スポーツを一生懸命できる才能があることは、忘れないで



スポーツ選手を見ている精神科の先生も、私以外にもたくさんいらっしゃるんですよ。ただ、「スポーツ精神科」がスポーツ業界にあまり浸透していないために、苦しんでいる選手と繋がれないことも多いんです。
スポーツ精神科の認知度がないせいで、通常の精神科を受診して、薬を飲みすぎてしまったり、「つらいなら引退すればいい」と言われてしまったり…。そんな状況を変えたい気持ちも強いんです。


選手自身が「回復するために休もう」と思うのは、やっぱりハードルが高いので。


選手が属しているチームやコミュニティで、いい環境だなと感じたところはありましたか?
選手にとっても、自分を見てくれている安心感がありますよね。なにかあったとき、相談もしやすいのではないかと思います。


でも、この前「こんなにメンタルが強い人は見たことがない」と言われたんです。真逆ですよね。


まぁ、私から見ると、自分が潰れてしまうまでがんばれた、自分を追い込むことができた時点で、すごく強い人だなと感じます。もちろん、潰れてしまう前にご相談いただきたいですけどね。


それでも、目標を見失って進めなくなっているなら、私のような人間がいることを思い出していただきたいです。支えになりたいと思っている人間がいますから。


患者さんも、選手の方と接しているとき、すごくいい表情をするんです。そんな顔、診察室では見たことないぞ!?と思ってしまうこともあります(笑)
それくらい、スポーツにはパワーがあるんです。もし、スポーツをやっていて、迷われている方がいたら、ぜひ講師をしていただきたいです。ご自身がやっていたことは決して無駄ではなかったことを、患者さんの反応からも分かっていただけると思います。


ご自身がスポーツで苦しみ、またスポーツに支えられた経験がある岡本先生。形だけの診察ではなく、選手の気持ちに寄り添い真摯に対応している姿が、言葉の端々から伝わってきました。
「誰にも相談できない、苦しい、スポーツなんてやるんじゃなかった」
そう思ってしまう前に、ぜひ“スポーツ精神外来”の存在を思い出してみてください。スポーツを楽しんでいたときの気持ちを、また、思い出せるかもしれません。
- 本コンテンツは、特定の治療法や投稿者の見解を推奨したり、完全性、正確性、有効性、合目的性等について保証するものではなく、その内容から発生するあらゆる問題についても責任を負うものではありません。
- 本記事は2019年11月1日に公開されました。現在の状況とは異なる可能性があることをご了承ください。




