
ネフローゼ症候群を受容していない私が患者・支援者として持つ希望
目次
ネフローゼ症候群、退院後の再発





ただ少し神経質にやりすぎていたかもしれません。



もちろん、塩分やナトリウムの量を毎回細かく調べていたのは勉強になりました。
ただ完璧主義になり過ぎて、それが守れない時には逆にストレスになっていたんだと思います。




口が乾いたら、含んで出すという感じでした。
入院中にたんぱく尿が出ている間は、腎臓に負担がかかるから蛋白質の制限があったり。
ただ、普段は「塩分の摂り過ぎ注意」や薬の飲み合わせで食べられないものがあったりくらいです。


でも今は、三食のトータルや、翌日の食事などでざっくりと帳尻合わせたりもしています。




たしかに、せっかく減ってきていた薬が再発する度にまた大量の服薬から再スタートするのはしんどいです。
でも、再発によって知見が積み重なっていくので、決してふりだしではないと思っています。


私も薬を飲むことを1ヶ月ボイコットしたことがあります。
いきなり止めるのは生命に危険が及ぶかもしれないのに、当時はどうでもよくなってて。


そのくらい追いつめられるので、再発で苦しんでいる人には「見えないところで積み上がっているものがあるから、ふりだしではないよ」と伝えたいと思っています。



当時の私は結局、最初の入院から数えて約2年間仕事を休みました。


食事を作ったり散歩したり、自宅で生活する訓練をしていました。


組織だからもちろんそうあるべきだし、もちろん迷惑もたくさんかけたんですけど。


不安や焦りで考えがひっちゃかめっちゃかになっていました。


上司がすごく良い方で、週イチでちょっと笑える営業の面白話をメールで送ってくれたり。







段階を踏んでフルタイムに戻していく「リハビリ休職制度」というものがありました。
最初は時短で、午前中だけ働いて徐々に時間を伸ばして慣らしていくのは良かったです。


医師とも復職に関してはずっと相談はしていましたが、私自身、本当に自信を喪失していて。
もしかしたら、本当はもっと早く戻れたかもしれませんが、「気分が乗らなかっただけ」なんて言えないですよね。笑


そこのホンネはしっかり記事にさせてもらいます。笑
長い人生ですしね。

復職、再発、そしてアメリカ



疲労感が溜まってきた時にたんぱく尿の検査紙で自分で尿を調べて、色が変わっていれば再発という感じ。


当時もふりだしに戻る感覚で、メンタルがヘトヘトでした。







いつ頃から行こうと考えていたんですか?
嫌になって主治医に愚痴っていたら、「田中さんの場合は環境要因もあるかもしれないから、思い切って変えてみたら?」と。


入院中のベッドから、エントリーシートを出して通っちゃいました。笑



「仕事でお金が入ると余暇に使えて心身ともにリフレッシュできるなあ」
「仕事をしている時は病気の事を忘れられるなあ、職場で人と話すのも気が晴れるなあ」
という感覚がぼんやりとあって。


アメリカ留学では福祉の勉強がメイン?


日本だと道端で知らない人にぶつかっても謝らない人も多いけど、少し当たっただけでもちゃんと謝る。
目があったらにっこりする。その洋服いいね!とほめてくれる。
もしここで私が体調不良で倒れていても、「きっと誰かが気にかけて助けてくれるだろう」という安心感がありました。


「この仕事さえできれば、障害があろうがなかろうがどっちでもいいよ」という考え。


それに「心身ともに健康」というワードって疎外感があるんですよね。



それに心身ともに健康な完璧な「健常者」って存在するんですかね?それは幻想な気がします。
みんな弱いところがあると思う。


LGBTとか人種でもグループがありましたね。






「配慮を受けるためには障害者雇用」みたいな1つのルートだけでなく、もっと働き方にバリエーションあってもいいのかなと思います。



元々、持っている素晴らしい個性もあるので、選択肢がもっとあれば広がるのになと思います。






その職場では気遣いのある優しい接客をしてくれていたんですね。
現在の社会では、その人の個性の前に健常者・障害者って括られる事もあるように感じますが、いつかその必要も言葉も無くなればいいと思います。
ちょっとした工夫や配慮で、職種を限らず、働きたい人の働く選択肢が広がればと思っています。




ただ、まず何からしてよいかわからず、それが焦りに変わってきてしまうこともあります。


今は職場復帰か休職か、いわば10か0を選択する状態。
でも、いきなり0から10というのは負荷が大きいので、希望者は少しでも仕事に携われるといいなと感じています。
アメリカのフードバンクでボランティアをした時、認知症の方も数時間そこで一緒に働いていました。
ケアされ続ける対象ではなく、出来る範囲で社会に貢献したいという気持ちを大切にしていると感じました。







ところが、2019年5月に再発して9月まで自宅療養をしていたんですね。
それを機に会社と相談して、復帰後は現場に戻るのではなく、もともと兼務をしていた企画のお仕事専従にすることになりました。


前よりもうまく時間が使えるようになって、治療と仕事の両立はよりしやすくなりました。


あとは週2回30分ずつ、大阪にいる上司とTV会議をしてコミュニケーションをとるようにしています。


私からは仕事の報連相や、仕事に直接関係のないちょっとした事も相談します。


体調の波はどうですか?






でも、今の上司は、オンラインでもちょっとした声がけが素敵で、色々な会話が出来ますね。


「くれぐれもご無理ないように」
「ベストじゃなくてベターでいいからね」
とか。じーんと効く言葉をいくつもくれるので、メモを取ってます。笑


「ご無理なさらず」とも言ってくれるので、ご無理しないようにしています。笑





不信感って相手が何をしているか、考えているかわからないというところから始まるので、リモートは特に意識的に多めに話す事が大事なのかも。


ネフローゼ症候群の患者会立ち上げ



どこかに同病の人もいるんだろうなと思いつつ、孤独に苛まれながら自己解決していました。




寛解と再発を繰り返すことで、治す気持ちが薄れていくというお話もお聞きしましたが、完治に対する思いに変化はありましたか?
あと、職場復帰して「治ったんだね」と言われるけど、実際は治ってないんだよなぁという悶々とした思いもあったり。
でも今は、いつかは完治すると思っています。
それをどれだけ早められるかが、私の中でのミッションです。



それでも、患者次第で完治できる病気になると信じています。




参加してみて、エビデンスが足りないんだろうなと思ったんですね。


他の患者会の例では基金を作って、自分たちが必要とする研究をおこなった医療者に対して、アワードとして研究費を渡しているらしいんです。


患者の立場としても、どういった研究を進めてほしいのかの意思表示にもなるので、今後ぜひやってみたいですね。


治る保証はないですけど、完治するという希望を持ち続けたいなと思います。


双方向であることが大事かと。


でも、途中から私の人生にとって味方になっていると感じてきました。


もともと無理しがちな私をネフローゼが再発をちらつかせながら、いい塩梅で見張ってくれています。笑
直視したくなかったムーンフェイスで丸くなった顔も「悪くないな」という境地にまで。笑


変わってしまった姿を直視出来なかったし、それは病の象徴でした。
本当の自分ではないんだとも思っていました。

――カメラマンの手が止まる
むしろ昔の写真が残ってなくて残念くらい。笑

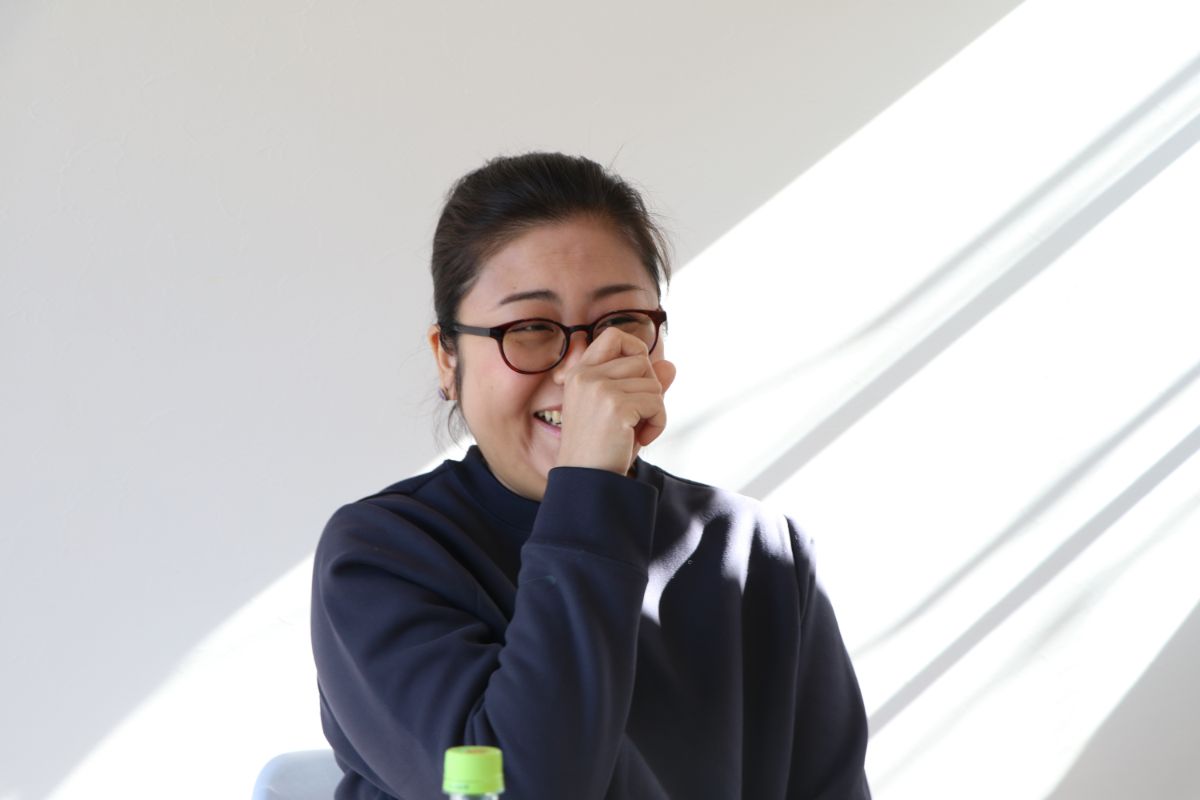
未だに受容はしていない

味方だと思うときもあれば、嫌だなって思うときも。




日によってプラスにもマイナスにもなるから、ゆらぎがあるものだと思っていて。


だから、一方的に「障害がある」と言われている側が、障害を受容する・しないという考え方自体がおかしいと思っているんですね。


「折り合いをつける」という言葉は同病の方が教えてくれました。しっくりきます。


ただ、同じ病気でも色々な考えがあるので、皆が皆、完治を目指さなくてもいいと思います。
解決法が無い中で完治のために努力するっていうのはすごくしんどいことだと思いますし。
それこそ折り合いをつけながら日々を大切に過ごすのも大事です。


ステロイドの副作用でうつっぽくなると自分でもコントロールできないし、予約外で主治医のところへ行ってボロボロ泣いてしまったり。
嫌だって思ったときに人に迷惑をかけている自分を認めながらも、どうやり過ごすか、という感じですかね。


これからやってみたいこと

難病のある方の中には、手帳がないことで働くスタートラインに立てない方もいます。
療養中に少し働ける仕組みなども含め、もう少し緩やかにいろんな働き方の選択肢を持てるような活動をしていきたいと思っています。




嫌になって勝手に薬をやめるよりも、そういうしんどい気持ちも伝えたりとか。
それは支援する中で利用者さんに教えてもらったというか、この仕事に就いてから、出来るようになりました。


人生のビジョンを共有して一緒に計画しながら、治療していきたいと思っています。



- 本コンテンツは、特定の治療法や投稿者の見解を推奨したり、完全性、正確性、有効性、合目的性等について保証するものではなく、その内容から発生するあらゆる問題についても責任を負うものではありません。
- 本記事は2020年3月8日に公開されました。現在の状況とは異なる可能性があることをご了承ください。




