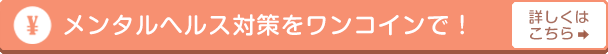ストレスチェック制度とは?企業はどう変わる?臨床心理士が解説
ストレスチェック制度のポイント
労働者の働き方を規定するものは労働基準法です。
労働基準法では賃金や、休み、契約に関することなどを規定しています。
一方で、労働者の安全や健康を守ることは「労働安全衛生法」に記述されています。
労働安全衛生法の改正によって「50人以上の事業場において、従業員に対して心理的な負担の程度をチェックする検査を行う」ことが義務化されました。
この改正のことが、俗にストレスチェック法案と呼ばれています。
ストレスチェック法案にはいくつかのポイントがありますので、まずきちんと押さえておきましょう。
・結果は、本人の同意なしに事業者が知ることはできない
・一定基準を満たす労働者から申し出があった場合は医師との面談を設定しなければならない
・面談の結果、必要な措置があれば医師の意見を聞いて実施しなければならない
このように、事業者に対する義務が増える内容になっています。
罰則規定はありませんが、電通事件など労働災害に対する社会的関心の高まり共に、行っていないことで社会的制裁を受ける可能性は高いでしょう。
また、ストレスチェックを行っていなかったことを根拠に、安全配慮義務違反が認められれば、民事裁判において多額の賠償金を支払うことも考えられます。
また、最初に述べた通り、労働者の安全を守ることが会社の生産性にもつながることを考えれば、実施しておいたほうが企業としての利益も大きいでしょう。
EAPへのニーズの高まり
EAPという言葉は聞いたことがあるでしょうか?
Employee Assistance Programの頭文字をとった言葉で、日本語では「従業員支援プログラム」と呼ばれています。
アメリカではベトナム戦争が終わるとその帰還兵たちが、アルコール依存やPTSD、うつ病などを患うという社会問題が起こりました。
民間企業の労働者でも、アルコール依存やPTSD、うつ病にかかる人が増え、企業の生産性は落ちていきました。
そんな中、労働者を支え、健康を守ることが企業の生産性の増加にもつながるという考え方が主流になり、事業者が労働者の健康のことを考えるプログラム、従業員支援プログラム(EAP)が生まれたのです。
EAPでは、多職種が連携しながら、労働者を支援していきます。
例えば、事業所の管理者が最近元気のない社員を見つけたら、話を聞き、人事部などと相談します。
必要があれば、人事の職員が産業医との面談を設定し、その改善を測るなどの動きがEAPと言えるでしょう。
EAPの種類には、外部の会社にすべて委託する外部EAPと、企業の中に専門チームを作る内部EAPなどがあります。
最近は、労働者の健康問題を専門に扱う会社も増えてきたこともあって、外部EAPが主流になってきています。
一長一短ありますが、外部EAPでは、コンサルタントからカウンセラー、産業医などすべてが揃っているので、専門的なプログラムをすぐに導入できるという利点があります。
内部EAPは、会社でチームを編成できるため、必要な職種を必要なだけ配置することが出来ること、自分の会社にあったプログラムの開発が出来ることに強みがあります。
ストレスチェック制度での企業の変化
うつ病などの精神疾患による休職が増加していること、電通事件をはじめとした過労死の問題が、社会的関心を集めていることもあり、企業のメンタルヘルスに対する関心は爆発的に高まりました。
そこに追い打ちをかけるように、ストレスチェック法案が可決されました。
「ストレスチェックを行なわなければならないけれども、どのように実施していけばよいのかわからない」という声を現場では多く聞きます。
義務になったから、実施すればいいというだけならば、厚生労働省が出しているストレスチェック表もありますし、健康診断の中でもストレスチェックを実施している病院も多くありますのでそういうものを利用していけばよいでしょう。
ただ、もし「会社の生産性を向上させるためにも本気で従業員のことを考えたい」というのであれば、思い切ってEAPを導入することをお勧めします。
アメリカの優良企業の中ではEAPを導入することはもはや常識となっており、その効果は誰もが認めているところです。
いきなり、EAPの専門チームを社内で作るのは抵抗があるというところは、外部EAPから導入してみるのが良いでしょう。
適切な予算で効果の高いプログラムを導入してくれるはずです。
働き方改革特集記事一覧
【第2回】【事例】働き盛りのうつを防ぐ…社員をうつにしないためには?
【第3回】ストレスと病気の関係、ストレスコーピングの3つの方法
【第7回】安全配慮義務とメンタルヘルス「4つのケア」の関係とは?
【第8回】EAPの役割とは?休職者を減らす事例を挙げて臨床心理士が解説
- 本コンテンツは、特定の治療法や投稿者の見解を推奨したり、完全性、正確性、有効性、合目的性等について保証するものではなく、その内容から発生するあらゆる問題についても責任を負うものではありません。
- 本記事は2017年2月22日に公開されました。現在の状況とは異なる可能性があることをご了承ください。